2013年02月26日
せがいの家Ⅱの冬季の温熱調査の分析結果1:考察その1…感を決める6つの要素
 「時ノ寿木組の家」
「時ノ寿木組の家」NPO法人時ノ寿の森クラブと協働した山から始まる家づくりの提案
「せがいの家Ⅱの冬季の温熱調査の分析結果1:考察その1…感を決める6つの要素
前々回のブログ、「せがいの家Ⅱの冬季の温熱調査の分析結果1」で得られた体感と室内温度との関係のズレは、何に起因するかを考察する、今回はその1。
■体感を決める6つの要素
我が家のこな数年の課題というか家族間の愚痴は、家の断熱性能が低くて暖房が利きにくい点にある、だから冬はリビングに家族が集まり、みんなで縮こまって暖を取っている、ので、せっかくの40坪の住まいも、使っているのはごくわずかと、もったいない状況に落ちいている。 `s(・'・;) エートォ
それはさておき、私たちが、寒さ厚さを感じ取る体感は、気温、湿度、気流、輻射(放射)、着衣、活動熱の6つの要素で決まる。
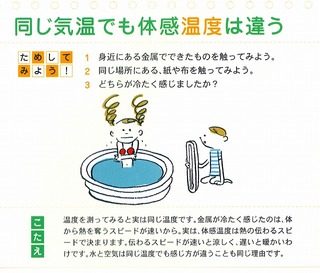 気温
気温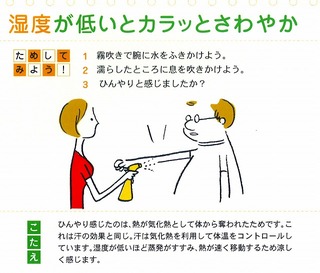 湿度
湿度 通風
通風 輻射
輻射最近は、エアコンで空気を暖めて暖を取る方法が主流だ、各室に1台という時代
…我が家と言えば「寒い冬は一枚余計に羽織り、温かい飲み物で暖を取る、暑いときは一枚脱いで、冷たい飲み物で涼を取る。」というすこぶるエコロジカルな手法が、我が家の主流で、家族の評判は良くない( ̄□ ̄;)!!。…
しかし*1)ジエボオンズの逆説どうり、家庭のエネルギー消費量は上がりっぱなしだ

冬季の室温測定から得られたdateの室内温度が、18℃~20.1℃と、高齢者に取っては低く、高齢者以外でも快適な温度の下限にやっと入るぐらいの温度でありながら、住まい手が快適と感じていた。
この落差は、エアコンのように、空気を暖めて暖を取る温熱環境と、輻射熱によりコントロールされた温熱環境の違いに起因し、快適で健康的な暮らしは、輻射熱が決め手だと言うことをこのdateは示している。
その理由は、床や壁・天井の表面温度が適度に保たれるから。
続きは次回に。
*1)イギリスの経済学者であるS・ジエヴオンズの名を取ったこのジエヴオンズの逆説とは
「エネルギーの利用効率の向上がエネルギー消費の減少をもたらすことはなく、その逆、消費を増大させる」という経済原則。
効率が上がれば、その財、サービスの価格が下がり、そのため需要は増大する。
Posted by pasarela at 21:03│Comments(0)
│パッシブデザインを活かす




















