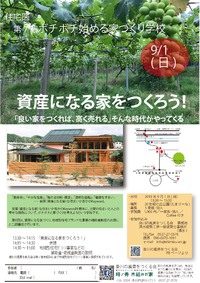2017年06月13日
最新建築が伝統建築に近づく
最新建築が伝統建築に近づく
下の画像は「空調も換気も断熱材も無いミニマムエネルギー・オフィスビル」と日経アーキテクチュア紙に紹介された「Baumschlager Eberle」という設計事務所のヘッドオフィスのブロック造のビル。

この一見何の変哲もないブロック造のオフィスを、なぜ取り上げたか。
”この建物は、建築家自らが長年興味を抱いてきた点、
(1)年間を通して室内を快適に保つため、躯体自体の断熱性能と蓄熱性能を高め、内部発熱(人、機器、照明など)のみで暖房を賄う。
(2)冷房・換気は開閉可能な窓だけで賄う。
といった試みを行った結果
”建物のたたずまいや構造のあり方などは、アルトバウ(Altbau=古い建物)と呼ばれるドイツの古い建物に近づいている。”
と設計者がコメントしている点に興味を覚えたからだ。
■断熱材を使わずに断熱
驚いた事に、このオフィスビルの第一の特徴は断熱材を使わずに高い断熱性能を有しているようだ。
”どういうこと?”と誰もが思われるだろう。
答えは、オフィスビルを構成しているブロックにあった、空気層のある断熱ブロックを使う事で、オフィスビルの高断熱化(U値=0.41)を実現していた。
断熱材は微細な空気層がを無数存在する方が性能が高い、気体は熱を伝えにくい(気体での熱の移動は対流が原因、なので、動かない空気が存在すると断熱性能が高まる)点にヒントを得たようだ。
建物の名前も2226とユニークだ
”室内の快適温度の範囲を意味する。暖房や冷房を使用せず、また躯体に比べて寿命の短い断熱材も一切使用せず、構造体だけで年間を通して室温22℃から26℃を維持するという意思”を表して命名したそうだ。
さらに興味深い事は
”断熱材を使わずに断熱とか、石油・発泡系断熱材の利用低減、リサイクル可能な材料の採用など、省エネ対策だけでなく、建築を構成する建材そのものの環境性能に意識がいっていることや、想定建物寿命を100〜150年にしている、その結果、現代建築が古い石造建築に通じるものに回帰した”と述べている点にある。
■最新建築が伝統建築に近づく
日本では、ほんの70年ほど前までは、地球環境とかサステイナブルとかグローバルな理念を振りかざさなくても、当たり前のことで、それを支える構法や技術は存在した。
近代の建築は、機能性や合理性を理念に掲げ、科学技術をあまりにも信奉するあまり、近代以前の構法や技術、材料を軽視してきた嫌いがある。
地球環境とかサステイナブルなどのグローバルな理念を旗印にしたとき”建物のたたずまいや構造のあり方などが、古い建物に近づく”とは愉快なことだ。
でも、そこに気が付いたときには”それを支える仕組みや職人がすでに散在しない”なんてこともあり得る点が気がかり。
下の画像は「空調も換気も断熱材も無いミニマムエネルギー・オフィスビル」と日経アーキテクチュア紙に紹介された「Baumschlager Eberle」という設計事務所のヘッドオフィスのブロック造のビル。

この一見何の変哲もないブロック造のオフィスを、なぜ取り上げたか。
”この建物は、建築家自らが長年興味を抱いてきた点、
(1)年間を通して室内を快適に保つため、躯体自体の断熱性能と蓄熱性能を高め、内部発熱(人、機器、照明など)のみで暖房を賄う。
(2)冷房・換気は開閉可能な窓だけで賄う。
といった試みを行った結果
”建物のたたずまいや構造のあり方などは、アルトバウ(Altbau=古い建物)と呼ばれるドイツの古い建物に近づいている。”
と設計者がコメントしている点に興味を覚えたからだ。
■断熱材を使わずに断熱
驚いた事に、このオフィスビルの第一の特徴は断熱材を使わずに高い断熱性能を有しているようだ。
”どういうこと?”と誰もが思われるだろう。
答えは、オフィスビルを構成しているブロックにあった、空気層のある断熱ブロックを使う事で、オフィスビルの高断熱化(U値=0.41)を実現していた。
断熱材は微細な空気層がを無数存在する方が性能が高い、気体は熱を伝えにくい(気体での熱の移動は対流が原因、なので、動かない空気が存在すると断熱性能が高まる)点にヒントを得たようだ。
建物の名前も2226とユニークだ
”室内の快適温度の範囲を意味する。暖房や冷房を使用せず、また躯体に比べて寿命の短い断熱材も一切使用せず、構造体だけで年間を通して室温22℃から26℃を維持するという意思”を表して命名したそうだ。
さらに興味深い事は
”断熱材を使わずに断熱とか、石油・発泡系断熱材の利用低減、リサイクル可能な材料の採用など、省エネ対策だけでなく、建築を構成する建材そのものの環境性能に意識がいっていることや、想定建物寿命を100〜150年にしている、その結果、現代建築が古い石造建築に通じるものに回帰した”と述べている点にある。
■最新建築が伝統建築に近づく
日本では、ほんの70年ほど前までは、地球環境とかサステイナブルとかグローバルな理念を振りかざさなくても、当たり前のことで、それを支える構法や技術は存在した。
近代の建築は、機能性や合理性を理念に掲げ、科学技術をあまりにも信奉するあまり、近代以前の構法や技術、材料を軽視してきた嫌いがある。
地球環境とかサステイナブルなどのグローバルな理念を旗印にしたとき”建物のたたずまいや構造のあり方などが、古い建物に近づく”とは愉快なことだ。
でも、そこに気が付いたときには”それを支える仕組みや職人がすでに散在しない”なんてこともあり得る点が気がかり。